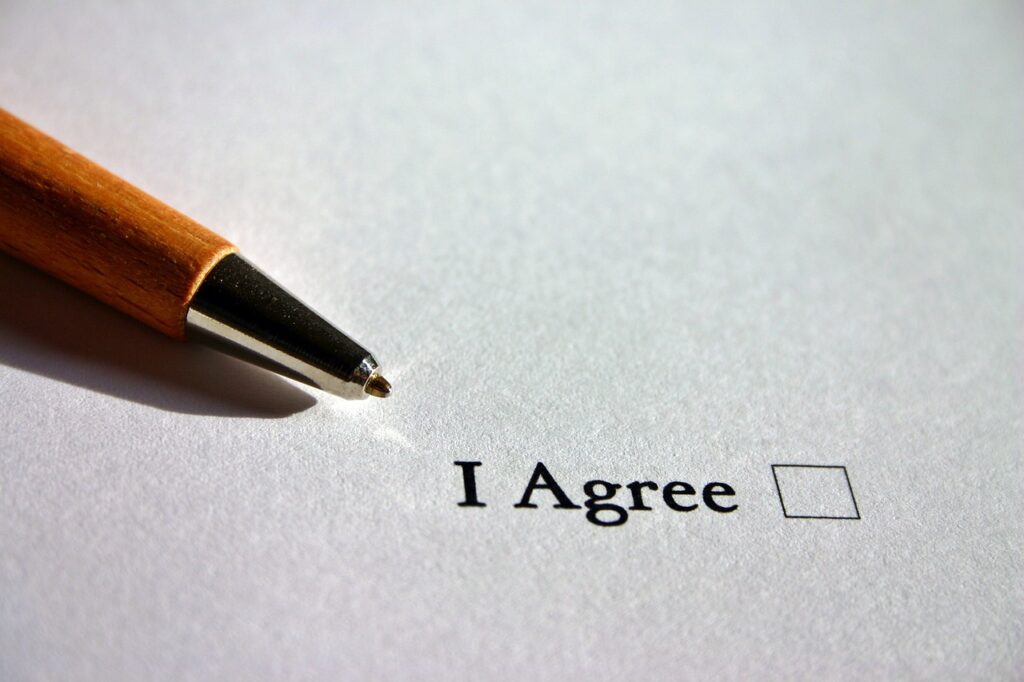今回は通訳や翻訳と著作権について、少し説明したいと思います。一見 関係が無い様に見えますが、実は通訳/翻訳と著作権には深い結びつきがあります。機械翻訳=Machine Translation / MTにおいても、著作権は無関係ではありませんので、今一度おさらいも兼ねてご紹介します。(CatkinによるPixabayからの画像)
そもそも著作権とは
著作権 / Copyright とは、そもそもナンなのか?ザックリと理解している人は多いと思いますが、今一度確認したいと思います。
公益社団法人 著作権情報センター Websiteより
著作権って何?
(はじめての著作権講座 )
「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。他人がその著作物を利用したいといってきたときは、権利が制限されているいくつかの場合を除き、条件をつけて利用を許可したり、利用を拒否したりできます。
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/
通訳 / 翻訳と著作権
小説など
創作物の翻訳
通訳や翻訳と著作権の関係、これについてパッと思いつくものと言えば、先ずは小説など創作物の翻訳ではないでしょうか?
以下記事でもご紹介しましたが、小説や戯曲、または歌の歌詞などの翻訳版や映像字幕には様々なバージョンがあります。
この「訳」はそれぞれ翻訳者が、原文を読んで考え、訳した著作物になります。
ですので、それぞれの「訳」は 訳した翻訳者が著作権を持ちますが、原作(訳す前のオリジナルバージョン)の著作者は別に居ますから、翻訳者は原作を利用した「二次的著作物」の著作者になり、原著作者と翻訳者の両方に著作権が与えられます。
海外の作品、例えば小説を日本語で翻訳するには、原則として翻訳権を取得する必要があります。
出版社が翻訳権を含む出版権を持つものに関しては、原作者の許諾を翻訳者が交渉して得る必要はありません。翻訳者は翻訳/出版権を持つ出版社から依頼された作品を翻訳します。
※出版社が翻訳/出版権を持っている作品で、原作者と出版社が翻訳して出版する事を交渉、許諾を得るさいに、原作者から翻訳者を指定される場合もあります。
出版社が出版権を持たない出版物を翻訳したい場合は、翻訳者が原作者と交渉して翻訳を許諾してもらう必要があります。
または、先に出版社にその翻訳したい本を持ち込み、その出版社に翻訳を含む出版権を獲得してもらってから、訳す場合もあります。
楽曲の歌詞の場合はレコード会社やレーベル、またはアーティスト自身の許可が必要となりますし、映像(映画や番組)の字幕については、放送局や制作会社、配給会社の許可が必要になります。
企業案件等の
翻訳について
企業案件における契約書やマニュアルを翻訳会社に依頼した場合の著作権の扱いも、実は小説等と同様です。
翻訳を依頼した企業が制作した契約書やマニュアル、資料の原文の著作権は依頼をした企業にありますが、翻訳したバージョンの二次的著作権は、翻訳会社または翻訳を担当した翻訳者が有します。
ただし、二次的著作権の扱いについては、翻訳を依頼する際に取り交わす契約書等によって定義される場合が多く、翻訳会社が二次的著作権を放棄する場合もあります。
逆に言うと、翻訳会社に翻訳を依頼する場合は、二次的著作権の扱いについての確認が必要ですし、二次的著作権を翻訳会社が放棄しない場合は、依頼内容以外での二次的利用の料金設定や、二次的利用の範囲等を確認する必要があると言うことです。
さらに現在は、AI翻訳 / 機械翻訳(Machine Translation / 略記 MT)についても注意が必要です。
例えば翻訳会社が機械翻訳を利用して翻訳をした場合でも、二次的著作権は翻訳会社に発生します。(契約書にて二次的著作権を放棄しない限り)
一方で、クライアントが依頼した機密などを含む文章を、翻訳会社が機械翻訳を利用して翻訳する事に問題は無いのか?と言った疑問もあると思います。これについては、一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会 が以下ページにて見解を示しています。
MTに関する法的問題について
(一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会)
https://aamt.info/act/journal/30th_anniversary/mt_information
通訳と著作権
話した言葉を「訳す」通訳にも、実は二次的著作権は発生します。
依頼された場所で通訳が訳した内容を、許可なく録音したり、撮影したりしたモノを使用する事や、録音した内容を文字にして印刷物にする事は、二次的著作権の侵害にあたります。
ただし、通訳者が訳した内容の二次利用についても、翻訳と同様に、依頼する際に取り交わす契約書等によって定義される事が多いです。
契約書にそう言った項目が無い場合は、翻訳と同様に二次的著作権の扱いについて確認をする必要がありますし、二次的著作権を通訳会社(通訳者)が放棄しない場合は、依頼内容以外での二次的利用の料金設定や、二次的利用の範囲等を確認する必要があります。
AIと著作権
現在、ジブリ風のイラストを生み出すAI画像についての話題が注目を集めています。
- 最新Chat GPTであふれる「ジブリ風」AI画像、威力示す一方で著作権問題も再燃(2025.03.28 CNN.co.jp)
- Viral Studio Ghibli-style AI images showcase power – and copyright concerns – of ChatGPT update (March 28, 2025 CNN)
また、イギリスでは1,000人以上のミュージシャンが集まり、英国政府の著作権法改正案に抗議するため『Is This What We Want?』という「無音」を収録したアルバムが、2025年2月25日にリリースされました。
- デーモン・アルバーンら、AIをめぐる著作権法の改正案に反対してサイレント・アルバムを共同で公開(2025.2.26 NME JAPAN)
- Damon Albarn, Kate Bush, Annie Lennox and over 1,000 artists release silent album to protest UK copyright AI laws (25th February 2025 NME)
AI / Artificial Intelligence や 生成AI / Generative AI の技術の進歩は凄まじく、この新たな状況の中で法的整備が追い付いておらず、以前にもご紹介したハルシネーションの問題など含め、様々な問題が山積しています。
著作権と言う観点から見ても様々な問題がありますが、その内の1つに AIに必要不可欠なディープラーニング / Deep Learning に関する問題があります。
通訳・翻訳にも前出した様に著作権(二次的著作権)は発生しますので、これらを使ってAIが学習をした場合、著作権の扱いはどうなるのか?
この「AIの学習」に関して、平成30年の著作権法改正により文化庁は以下の様な見解を示しています。
AI開発・学習段階 (法第30条の4):AI開発のための情報解析のように、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為は、原則として著作権者の許諾なく行うことが可能
AI と著作権に関する考え方について - 文化庁(2024/03/15)
また、人工知能に関する統一ルールを定めたEU AI 規則の全訳は 公益社団法人 著作権情報センター (CRIC)の外国著作権法ページに掲載されています。
本規則の全訳は 井奈波朋子弁護士(龍村法律事務所パートナー弁護士)が、英語版と仏語版の双方を参照しつつ、できるだけ分かりやすくなるよう翻訳をされたとのこと。
通訳や翻訳に関しては、機械翻訳に関する話題が注目されがちですが、AIの進歩において著作権に関する問題も重要なことの1つと思い、今回は本記事にて紹介させて頂きました。
なお、公益社団法人 著作権情報センター (CRIC)には外国著作権法を始め、通訳者・翻訳者にとっても知っておきたい著作権の情報やセミナーの開催情報などが紹介されています。ご興味のある方は、ぜひ1度チェックされてみては如何でしょうか?
公益社団法人 著作権情報センター Website
https://www.cric.or.jp/index.html